- 「三井ホームに決めて本当に後悔しない?」
- 「打ち合わせが多すぎて大変そう…」
- 「決めてよかったポイントを知りたい」
私たちも家づくりを始めたとき、同じような悩みや疑問を抱いていました。
特に注文住宅は「自由に決められる分、迷いも多い」。
後悔しないためには、何をどう考えるべきか──
それを明確にするのが一番難しいんです。
この記事では、実際に三井ホームと家づくりをした私たち夫婦が、
打ち合わせで「これを選んでよかった」と感じたポイント5つを紹介します。
毎日をどう快適に過ごせるか?
迷いの中でどう選べば納得感が残るのか?
そのヒントが詰まった内容になっています。
「面倒だった打ち合わせ」が、結果的にいちばん価値ある時間だった。
そんな実感を込めて、後悔しない家づくりの視点をお届けします。
全館空調を選んだ理由

以前住んでいたメゾネットのアパートでは、特に夏の2階がとにかく暑く、家を空けると室温は30度後半になることも普通でした。
共働きの我が家では、妻が先に帰宅することが多く、まず最初に部屋を冷やす作業から始めなければなりませんでした。
「空調を整える時間」が1日のルーティンになっていたんです。
決め手は「営業さんの体験談」と「数字で見た合理性」
スマートブリーズワンの導入は正直迷いました。
価格は高く、家電量販店で気軽に買い換えるものでもありません。乾燥や電気代も気になります。
でも決め手になったのは、担当営業さんが自宅で実際に使っていたという事実。
家族構成も近く、使い勝手をリアルに聞けたことで、将来の暮らしがイメージしやすくなりました。
ただ、それだけではありません。
我が家の構成だと、通常はエアコンを4台設置する必要があります。
しかもリビングは吹き抜けなので、出力の強い機種が必要。
エアコンの耐用年数は一般的に6年、長く見積もっても10年。
一方スマートブリーズワンは15年程度。
30年スパンで見れば、交換コストの差はむしろ全館空調の方が有利だと説明を受け、自分でも調べて納得しました。
正直、営業さんが使っていなかったとしても、最終的には選んでいたと思います。
それだけ、数字と合理性に納得できたという感覚があります。
実際に使ってみて感じたこと
- 家の中の温度差がゼロに
→ 帰宅直後から快適。廊下・洗面所・階段下まで同じ温度なのは想像以上の快適さ。 - 夜泣き対応がスムーズに
→ 子どもが泣いたときに、どの部屋に移動しても寒くない・暑くない。これは本当に助かっています。 - 掃除の手間が想像以上に少ない
→ 壁掛け4台分の掃除が不要。3ヶ月ごとに交換ランプが点灯し、15分ほどで完了。
→ メインフィルターは月1回、掃除機で吸うだけ。実際それで問題なし。 - 夫婦の負担が減った実感
→ 妻の「まず部屋を冷やす/暖める」作業がゼロに。精神的にも肉体的にも余裕が生まれた。
検討中の方へ伝えたいこと
「営業さんが使っているかどうか」ももちろん参考になりますが、
冷静にコスト・メンテ・快適性を比較するだけでも、全館空調の価値は十分に見えてきます。
初期費用や乾燥への不安がある方は、ぜひ他記事もご覧ください
吹き抜けの納得と後悔

寒い?まぶしい?──迷ったからこそ得られた納得感
吹き抜けを取り入れるかどうかは、家づくり初期からかなり迷ったポイントでした。
開放感やデザイン性には惹かれつつ、「冬は寒いのでは?」「まぶしすぎない?」「思ったより暗くならない?」という不安があったのが正直なところ。
特にリビングの快適さは、家族全員の生活満足度に直結すると考えていたので、見た目だけで選んで後悔したくないという思いがありました。
採光・通風・安全性──プロの提案で見えた納得設計
最終的に吹き抜けを採用したのは、設計士さんからの丁寧な図解と立地を踏まえた具体的な説明があったからです。
- 両側が道路に挟まれた土地で、高さ制限がかかる区域だったため、日照が遮られる可能性が低い
- 南と東に設けた高窓からの光が、1階奥まで届く図面を提示してくれた
- 吹き抜けによる気温のムラは「シーリングファンで風を循環すれば解消できる」と説明
「見た目がいいから」ではなく、「生活面でも合理的」と納得して採用できたのは大きなポイントでした。
ロールスクリーン&シーリングファンで快適性を保つ
高窓には電動ロールスクリーンを採用しました。
最初は手動も考えましたが、「子どもが紐に首を絡める危険がある」と聞き、電動に決定しました。
操作は快適で、ストレスもなく見た目もすっきり。シーリングファンとの干渉もありません。
- 採用したのは、ある程度光を通すタイプ
- 基本は閉じたままでも、日中は照明が不要なほど明るい
- 暑さ寒さのムラはシーリングファンの風循環で快適に保たれている
ひとつだけ後悔したこと
吹き抜けの上部にある主寝室の窓に、カーテンもスクリーンもつけなかったのは反省点です。
私の帰宅が遅くなる日、妻が寝ている時間にリビングの明かりが寝室まで差し込み、睡眠に影響を与えてしまう場面がありました。
初回点検で相談したところ、三井ホームの製品でなくても後付け可能とのことでした。
自前でロールスクリーンを用意し、施工してもらいました。
ちなみにこの窓はシーリングファンを上から掃除するために設けたアクセス窓でもあり、子どもの安全性を考えて開閉範囲と高さも調整。この点も担当者の助言を活かしました。
結果として、吹き抜けは我が家の正解だった
採光性・空調効率・開放感──どれも期待以上で、生活の質を引き上げてくれる存在になりました。
「明るいけれどまぶしくない」「空間が広く感じるけれど寒くない」。
このバランスは、プロとじっくり相談しながら設計できたことが大きかったと実感しています。
収納と動線のこだわり

収納は多ければいい…とは限りません
よく言われる「収納は多いほうがいい」という言葉。でも我が家は、そう単純ではありませんでした。
妻はミニマリストというほどではないものの、物を増やしたくないタイプです。
一方の私は、一度持った物をなかなか捨てられないタイプで、引っ越しを何度か経験する中で「そもそも買わないのが一番の対策」と実感するようになりました。
そんな2人が選んだのは、必要な物を厳選し、その分だけ収納を用意するスタイルです。
収納の量ではなく、収納の“質”と“位置”を重視した結果、リビングや寝室の広さも確保できました。
必要なところに、必要なだけ
- 洗面スペース+小クローク
洗面脱衣室に小クロークを併設し、その場で着替えが完結するように設計しました。ドアと鍵を設けており、現在は子どもの脱走防止にも活躍しています。 - キッチン横の作業スペース
リビングの壁面に作業スペースを確保しました。将来の子どもの宿題や妻の作業を見越して設置しています。 - ファミリークローク+子ども用収納
寝室とつながるファミリークロークは在宅勤務やリモート会議にも使えます。ハンガーや棚は後から高さを変えられるタイプを採用し、子どもの成長や生活の変化にも柔軟に対応可能です。
キッチンにこそ“生活感のなさ”を
- 吊り棚はあえて設けませんでした
高くて届かない・物が落ちるといった不便を回避しています。 - ゴミ箱専用スペースを確保
導線を妨げず、見た目もスッキリしました。 - 下部収納+パントリーで十分な収納力
棚がなくても不便は感じていません。 - 回遊動線設計で副産物も
セカンド冷凍庫を自然に置けるスペースが生まれました。
高さの調整は“気づいてもらえた”から
我が家のキッチンは、通常よりも少し高めの仕様にしました。
この選択は、担当者が「奥さまも背が高めですし…」と気づいて提案してくれたことがきっかけです。
建売や賃貸では当たり前だった“低めのキッチン”では、私自身も腰に負担を感じていました。
今では調理中も姿勢がラクで本当に助かっています。
こうした細かな配慮ができる営業さんと出会えたことも、満足感の大きな理由のひとつです。
なお、キッチン背面の収納と作業スペースはあえて一般的な高さに設定しています。
これは、高めの規格では気に入るデザインがなかったことに加え、将来的に子どもが調理を手伝うことを考えると標準の高さのほうが使いやすいと考えたためです。
今のところ、不満はありません
収納と動線が自然にリンクしているため、暮らしていて困ることがほとんどありません。
「こうだったらいいな」と思っていたことのほとんどが、設計段階で形になっていたという実感があります。
ちなみに、階段下の余ったスペースは、子どもの遊び道具を収納する場所として活用しています。
もともとは将来ペットを飼うことを考えて“家の形”にしたのですが、息子がとても気に入り、今では秘密基地のような空間になっています。
このように、設計段階では収納として見ていた場所が、子どもの成長に応じて思わぬ役割を果たすこともあります。
読者の方へ伝えたいこと
- 収納は“何を入れるか”を決めた上で設計すると、無駄がありません。
- 動線と収納が連動していれば、小さなストレスが積み重なりません。
- パートナーと収納・物に対する価値観をすり合わせておくと、設計段階で迷いが減ります。
暮らしやすさを支える細かな工夫

「ここ、こうしておいてよかった」と思えるポイントは、実は毎日使うような細かい場所にこそ多くありました。
打ち合わせ当時には気づけなかった部分も、担当の方や家族の経験から教えてもらい、形にできたことがたくさんあります。
夜中でも安心の足元ライト
廊下と階段には、人感センサーで点灯する足元ライトを設置しました。
夜中にトイレへ行くときも、上の照明をつけずに移動できるので、家族の睡眠を妨げることがありません。
また、災害などの非常時にも、避難経路の明かりとして機能してくれる安心感があります。
来客との距離感を調整できる玄関まわり
インターホンは玄関扉のすぐ横ではなく、少し離れた場所に配置しました。
これは、妻が幼少期に「玄関を開けたら人と目が合って怖かった」経験があったためです。
その対策として、玄関の向きを道路に対して垂直にし、壁を伸ばして視線が抜けすぎないよう調整しました。
来客との距離感を保ち、精神的にも落ち着く設計になっています。
コンセントは多めに設置、床にも配置
コンセントは「あとから増やすのは大変、でも増やす分には追加料金なし」という考えで、迷ったら設置する方針にしました。
床コンセントも2ヶ所導入。片方は使用頻度が高く、もう一方はソファの下でふだんは閉じたままですが、どちらも設置してよかったと感じています。
浴室・洗面は“掃除のしやすさ”重視
浴室はあえて鏡や棚を最小限にし、掃除の手間を減らす構成にしました。
浴槽も小さめで十分と感じていたので、その分スペースも有効に使えています。
また、洗面は玄関横と脱衣スペースの2か所に配置しました。
来客は玄関横を使用し、プライベートな洗面所には基本的に入らない設計にしています。
インテリアはプロと一緒に選定
カーテンやロールスクリーンの選定には、三井ホームのインテリアコーディネーターの方に同席いただき、空間になじむ落ち着いた色味で統一できました。
自分たちだけでは迷ってしまいそうな部分も、専門家の視点で的確なアドバイスがもらえたことは、とても心強かったです。
土間収納と視線のコントロール
玄関横には引き戸付きの土間収納を設け、来客から中が見えないように工夫しました。
玄関から洗面所や室内が直接見えない構造になっており、生活感が出にくい点も気に入っています。
外壁は“汚れにくさ”で選択
三井ホームでは標準で吹き付け塗装+ブロック・アンド・シームレスウォール(BSW)が採用されており、汚れやひび割れ対策がきちんとなされた外壁です。
さらに我が家では、オプションで「こて仕上げ(トラバーチン仕上げ)」を選択。
表面が滑らかになることで、さらに汚れがつきにくく、白さも2年目の今なおきれいに保たれています。
暮らしてわかった“決めてよかった”の本質
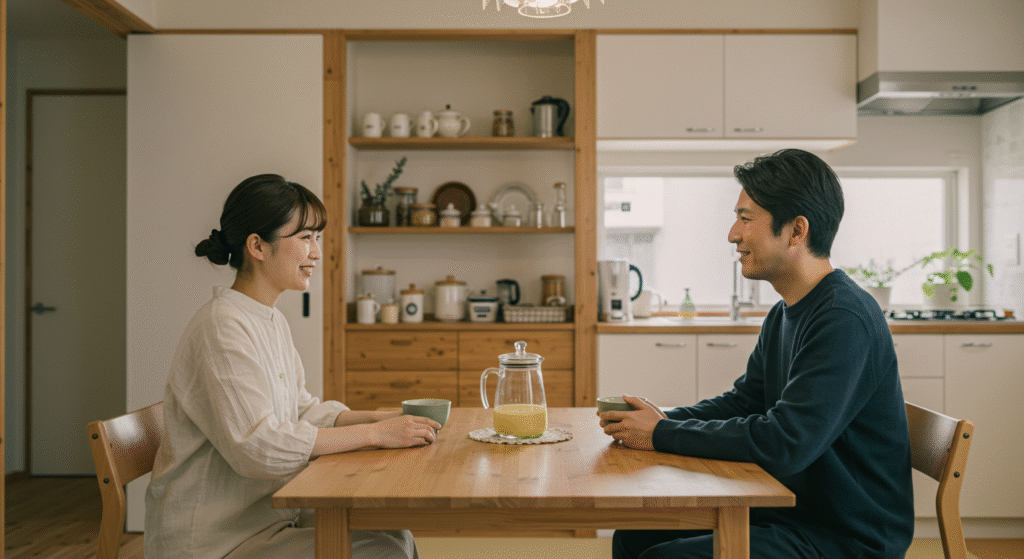
家づくりの打ち合わせ中、「ここまで細かく決めるの?」と思った瞬間が何度もありました。
それでも、時間をかけて一つひとつ考えた結果、住みはじめてから「あれを決めておいてよかった」と思える瞬間がたくさんあります。
むしろ、打ち合わせのときにはそこまで深く考えていなかった部分が、意外と日々の暮らしを支えてくれている実感があります。
信頼できる担当との対話が後悔を減らした
今回紹介した内容の多くは、営業担当さん・設計士さん・インテリアコーディネーターさんとのやりとりの中で生まれたものでした。
「本当にその仕様が必要なのか?」と迷ったときに、
我が家の生活パターンや将来設計を一緒に考えてもらえたことが、後悔の少ない家づくりにつながったと感じています。
これから家づくりをする方へ
もしこれから三井ホームや他のハウスメーカーで家を建てようとされている方がいたら、
「面倒だな」と感じる打ち合わせこそが、後悔しない家づくりのために最も大切だったと、実際に建てた今だからこそお伝えします。
暮らしのイメージをひとつずつ言葉にしていく作業は、
「今の自分たちにとって本当に大事なことってなんだろう?」と向き合う時間でもあります。
まとめ
- 満足感の理由は「打ち合わせの質」
丁寧に一つずつ決めていけたことで、後悔のない家づくりにつながった。 - 担当者との信頼関係が安心材料に
営業・設計・インテリアコーディネーターが、我が家に合った選択を一緒に考えてくれた。 - 標準仕様も万能ではないが、納得して選べた
すべてが理想通りではないが、暮らしに合うよう取捨選択できたことで満足感がある。 - 家づくりは「どう決めたか」が将来の納得に直結する
仕様よりも、選ぶ過程の丁寧さが「この家でよかった」と思える要因になる。 - 三井ホームを検討中の方へ
設備やデザインだけでなく、「一緒に決めていけるかどうか」という視点でも、パートナー選びをしてみてください。
一つでも参考になることがあれば嬉しいです。
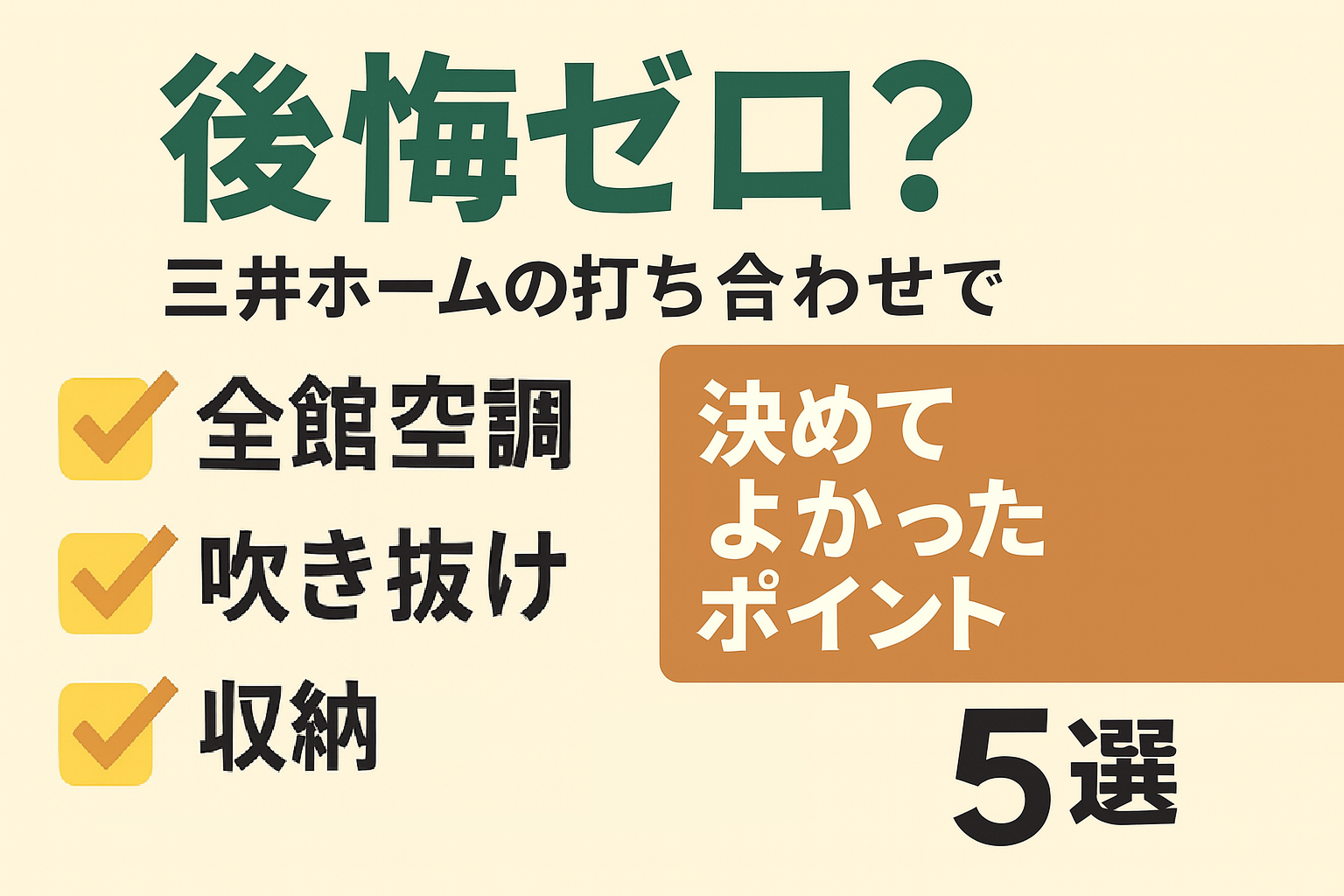
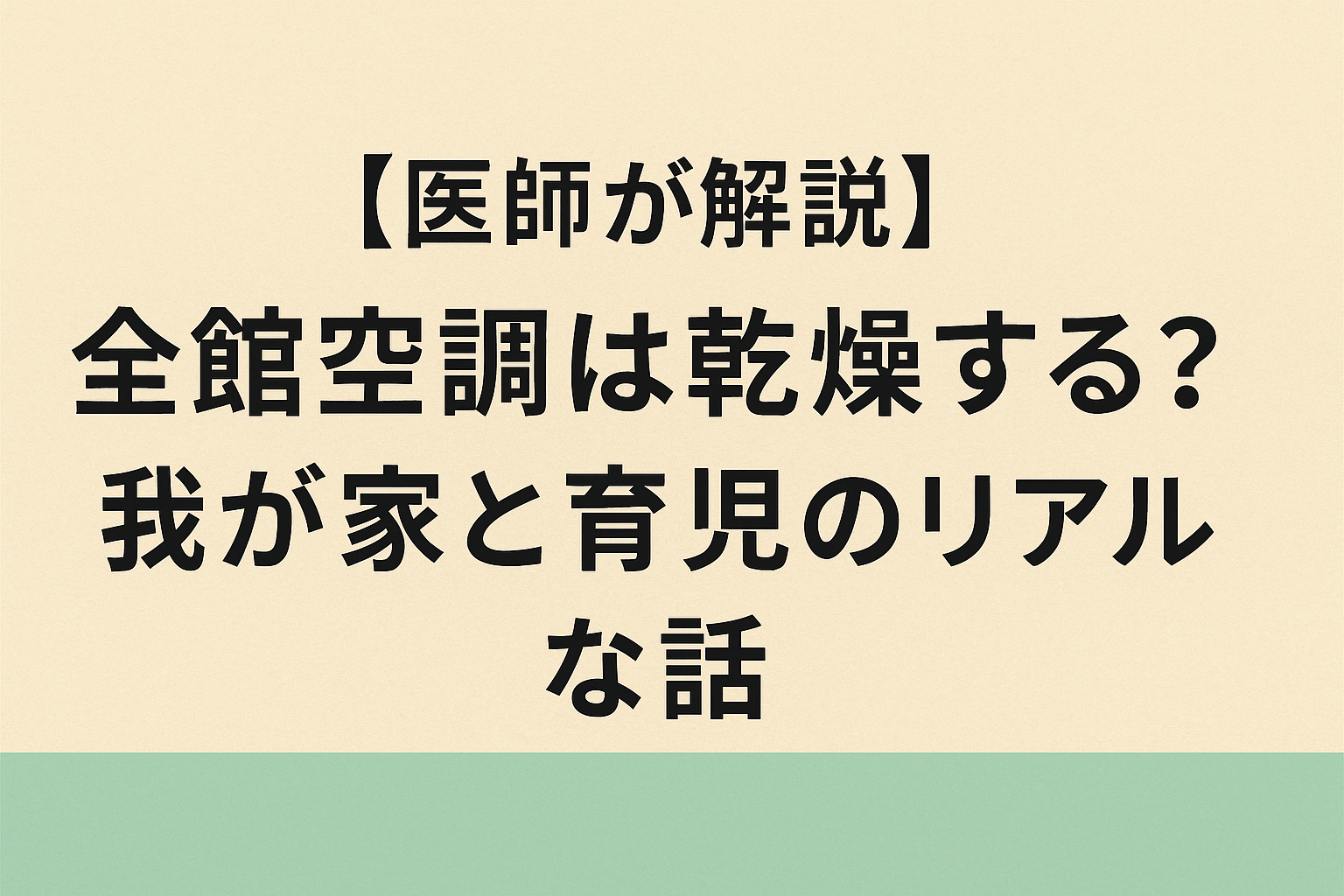
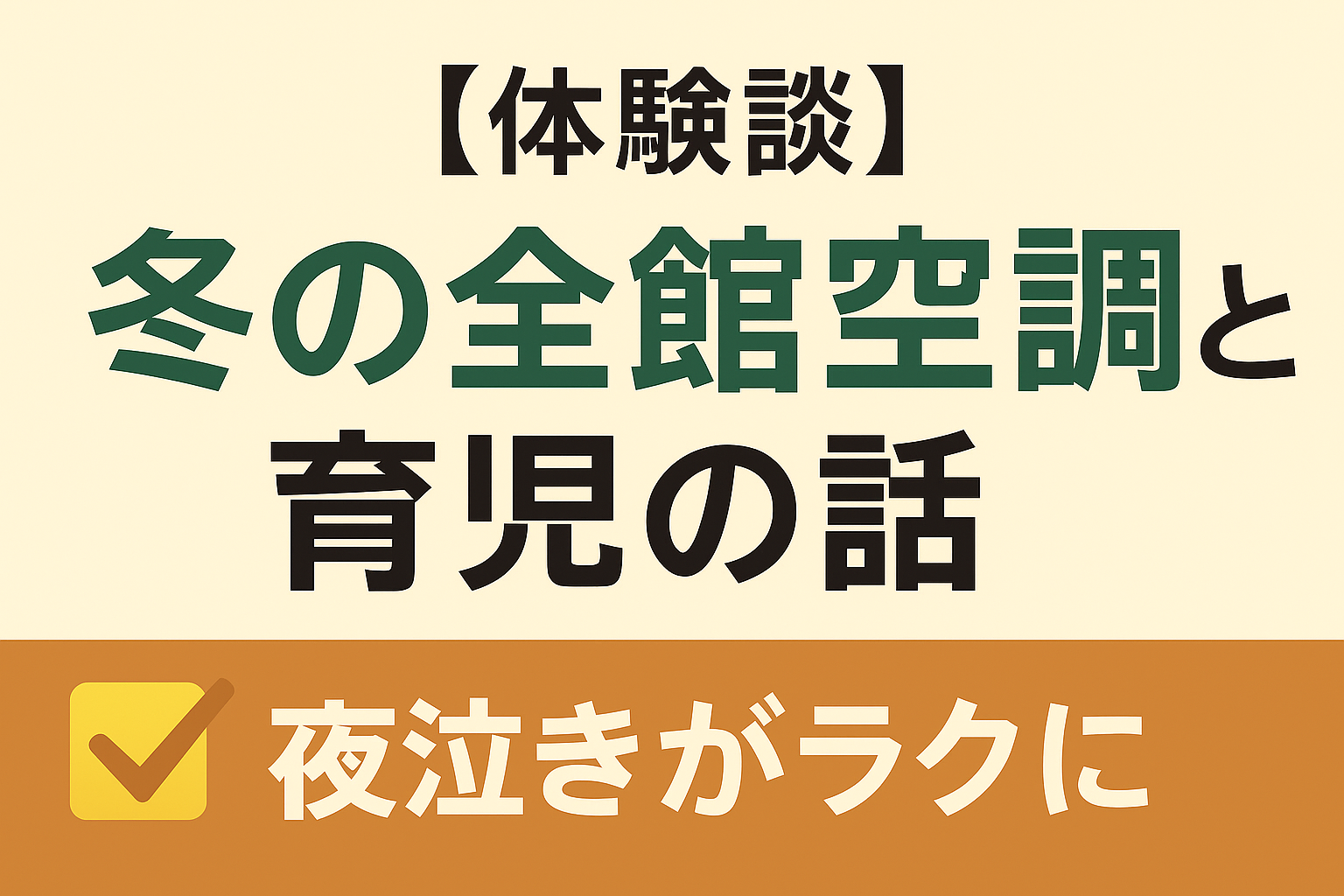
コメント